次のようなコメントが来た。
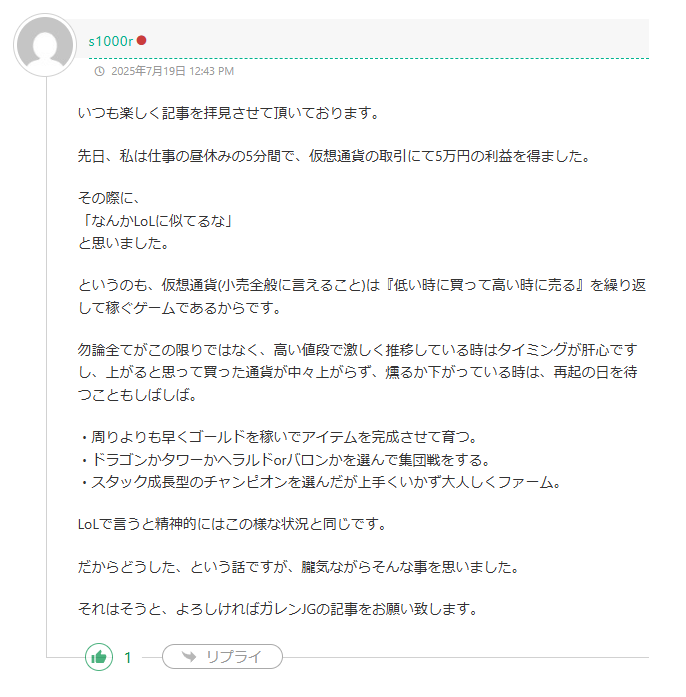
言葉のクラスタというのが離れているので、
簡単に解釈できる文章ではないが、
なんとなく言っていることはわかる(気がする)。
LoLのゲームの難度は試合によって違う。
あらゆる試合で足を引っ張らない実力がある場合、
試合は次のようになる。
- 何をやっても勝てない試合(難度10)
- 自分が対面に3回ソロキルされても勝てる試合(難度0)
難度5か6くらいで勝てれば、
やっとレートが上がっていくと思っていい。
とにかく難度0の時に、
あなたの意思決定の質がゲームから問われるケースは少ない。
難度が高くなればなるほど、
ゲームからあなたの日頃の意思決定の質が求められるわけだ。
今回は有名な「Thinking in Bets」の内容を紹介したい。
日本語版だと「確率思考 不確かな未来から利益を生みだす」となっている。
プロのポーカープレイヤーが書いた、
意思決定の本である。
ティルトというのはポーカー用語なので、
この本を読めば他のLoLプレイヤーに対して”差”を付けることができる。
この記事がパッチ25.14の時に執筆されました。
意思決定の質とは何か
意思決定の質とは、結果の質とは区別されるものだ。
素晴らしい結果が
必ずしも素晴らしい意思決定によってもたらされたわけではなく、
悪い結果が
必ずしも悪い意思決定によってもたらされたわけではない、
という認識が重要である。
良い意思決定は、
次の要素を含む良いプロセスから生まれる
- 自身の知識の状態を正確に表現しようとすること。
- 不確実性を受け入れ、自分がどれだけ不確実であるかを把握しようとすること。
- 多様な結果が起こる可能性を最大限に推測すること。
ポーカープレイヤーが結果の質と意思決定の質を区別することについて警告する
「結果主義(resulting)」
という言葉があるように、
私たちはしばしば意思決定の質と結果の質を結びつけがちである。
- 意思決定は良かった、結果も良かった
- 意思決定は悪かった、結果も悪かった
- 意思決定は良かったが、結果は悪かった
- 意思決定は悪かったが、結果は良かった
単純に4パターンで考えると、
結果主義は
- 結果が良ければ、意思決定は良かったはずだ
- 結果が悪ければ、意思決定は悪かったはずだ
の2択になるので、
実質
- 結果だけで決めてるので、意思決定を無視している
のに等しい。
私のTFTはこのレベルである。
このレベルのプレイヤーと進んで会話したいTFTプレイヤーは存在しないはずだ。
意思決定の質を妨げる要因
意思決定の質を低下させる一般的な人間の傾向や、
認知バイアスをいくつか上げよう。
- 結果主義(resulting): 自分の意思決定の質を、その結果の質と同一視することです。良い結果が出れば良い意思決定だったとみなし、悪い結果が出れば悪い意思決定だったと考えるパターンです。
- 確実性の幻想: 「私は知っている」「確信している」といった言葉に表れるように、物事が実際よりも確実であると過信する傾向です。
- 自己奉仕バイアス(self-serving bias): 良い結果については自分の功績とし、悪い結果については運のせいにする傾向です。
- 確証バイアスとフィルターバブル: 既存の信念を裏付ける情報を探し、反対意見を避ける傾向です。インターネットの「フィルターバブル」はその一例です。
- 時間割引(temporal discounting): 将来のより大きな報酬よりも、現在の小さな報酬を不合理に優先する傾向です。
- ティルト(tilt): 感情的な動揺により、意思決定の判断が損なわれる状態です。ポーカーで用いられる用語ですが、日常生活でも瞬間的な出来事を過度に重視し、感情的な反応を示すことがあります。
1 他人に対して無責任に発言する分には構わないが、
自分自身には絶対に使いたくない考え方だろう。
2 それなりのレートのプレイヤーならば、
1人の例外もなくこのバイアスは克服しているはずだ。
LoLは「思ったのと違う」というケースが頻繁に発生するからだ。
「第一印象」と「事実」がかけ離れていることが多く、
そこを区別できない人だと思われると、
「LoLの話をするに値しない人物」という扱いをされる。
3 バイアスという名の通り、
「普通の人間が普通に振る舞うとこうなりがち」
というヤツだ。
気持ちはわかるのだけど、
こういう態度は芋臭い。
なので、あなたが手練れのプレイヤーならば
- 負けた試合は「俺が悪かった」
- 勝った試合は「味方が強かった」
みたいな振る舞いをしたほうがいい。
4 負けを認められないバカの態度は共通している。
そういう人間は後から取って付けたようなデータを持ってきて、
論理的な態度を装いつつ、
再度レスバトルを仕掛けてくるのだ。
人間は悔しいと、そういうことをしてしまいがちだ。
漫画などの物語だと、
信念という言葉は良い意味で使われるが、
他の場所だと大体悪い意味で使われる。
5 「貧すれば鈍する」ということわざがあるように、
大昔から知られていることである。
貧乏だと何をするにもリスクが高くなるので、
脳みそがサバイバルモードになるからだ。
6 LoLでも使われる言葉なので、
詳しく説明しよう。
友人に話せばドヤッとできること間違いなし😎
ティルトとは何か?
ポーカーにおける「ティルト(tilt)」とは、感情的な動揺によって意思決定の判断が損なわれる状態を指します。
この概念は、もともと伝統的なピンボールマシンから来ています。ピンボールマシンは、プレイヤーがボールの動きを変えようとして激しく揺らすと、内部のセンサーが作動してマシンが機能停止し、フリッパーが動かなくなり、「tilt」という文字が点滅するようになっていました。
このピンボールにおける「tilt」の語源が示すように、人間の脳内で「ティルト」の瞬間に起こることは、揺さぶられたピンボールマシンに似ています。具体的には、脳の感情中枢(特に扁桃体を含む大脳辺縁系)が活発になり始めると、意思決定を司る前頭前野の機能が停止してしまうと説明されています。これにより、私たちは「認知的制御センター」をシャットダウンしてしまうのです。
ポーカーにおいて、プレイヤーは、スコアボードの変動のように、直近の変化に感情的に、かつ不釣り合いに反応することで「ティルト」に陥るリスクがあります。このような状態に陥ると、「意思決定に適した状態ではない」とされています。
「ティルト」はポーカーの専門用語ですが、日常生活においても、瞬間的な出来事を過度に重視し、感情的な反応を示す際に同様の現象が見られます。これは、良い意思決定を妨げる要因の一つとして挙げられています。
LoLならいくらティルトしても笑い話で済む。
逆に私くらい慣れると
LoLでは何が起きてもティルトしないが、
それはそれで面白さは損なわれているような気がする。
日常生活でティルトすると大変だ。
意思決定の質を向上させるための戦略
1. 「よくわからない」を受け入れる勇気を持つ
多くの人は、「自信がない」と思われることを恐れて、
不確実なことに対しても断定的な態度を取りがちだ。
しかし、「よくわからない(I'm not sure)」と素直に言えることこそ、
より良い意思決定者になるための第一歩である。
これは、客観的な真実が存在しないという意味ではなく、
真実に近づくための、開かれた姿勢なのだそうだ。
自分の「確信度」を
- 「全くない(0)」か「確信している(10)」
の二択ではなく、
0から10までの尺度で表現してみよう。
これによって
「白黒思考」や「全か無か思考」を抜け出すことができる。
LoLのレーン戦をこんな大雑把に考えてるヤツがいたら、ただのLoLできないヤツだ。
なので態度、やる気、レディネスの問題なんだろう。
2. 意思決定を「賭け」と捉える
人生におけるすべての意思決定は、
ある意味で「特定の将来に対する賭け」だ。
私たちは意識的であれ無意識的であれ、
常に「もしこうしたら、こうなるだろう」という予測に基づいて行動している。
たとえば、新しいスキルを学ぶことは、
将来それが役立つという「賭け」である。
最近気付いた、人間が好きなのはガチャ要素と計画を立てることの2つだなと。
3. 結果から意思決定を分離する
私たちはしばしば、
「結果がうまくいかなかった=意思決定が間違っていた」
と考えがちだ。
しかし、これは危険な思い込みである。
結果がどうであれ、
その意思決定に至るプロセスが適切だったかどうかは、
別の問題だ。
アリーナでギャンブラーの剣を選んで8位だったとしても、意思決定が間違っていたわけではない。
と思いたい。
4. 真実探求グループ(truthseeking groups)を活用する
社会学者のロバート・K・マートンは、
科学コミュニティの理想的な規範を「CUDOS(キュードス)」という頭字語で示しました。これらの規範は、科学的な探求を促進し、
知識の信頼性を高めるための行動原則として提唱されましたが、
真実を追求するあらゆるグループにも広く適用できます。CUDOSは以下の頭文字から構成されています。
- Communism (データ共有): 自分にとって都合が悪い情報であっても、隠さずにオープンに共有しましょう。正確な評価のためには、すべての情報が必要です。
- Universalism (普遍主義): 意見の内容を評価する際に、誰が言ったか(例:「専門家だから」「あの人が言ったから」)ではなく、意見そのものの価値で判断しましょう。個人的な属性に左右されてはいけません。
- Disinterestedness (無私): 意思決定の評価を行う際、結果を知ることによるバイアス(結果主義)に注意し、中立的な立場を保ちましょう。可能であれば、結果を知らない状態で意思決定の質を評価する「結果盲目分析(outcome blindness)」も有効です。
- Organized Skepticism (組織化された懐疑主義): グループ内で異なる意見や批判的な視点を歓迎し、常に互いの信念の正確性を疑い、検証する姿勢を持ちましょう。健全な議論が、より良い結論へと導きます。
「Sどこ?」
と私は思ったが、
Organized SkepticismのSらしい。
友人はこういう性格的な特性を持つのが望ましいらしい。
5. 心的時間旅行(メンタル・タイムトラベル)
- 過去と未来の自分を意思決定に巻き込む: 現在の意思決定に、過去の経験や将来の結果を考慮に入れることで、より合理的な選択が可能になります。
- ユリシーズ契約 (事前約束): 感情的で非合理的な決定を防ぐために、事前に特定の行動を約束するものです。例えば、飲酒時に配車サービスを利用するなど、将来の自分が非合理な行動をとることを予測して、その行動を物理的に、または心理的に阻止する障壁を設けます。
- 意思決定誓い瓶 (Decision swear jar): 非合理性を示す言葉や思考パターンを特定し、それらが出たときに立ち止まって考える習慣を身につけることです。
- 偵察 (Reconnaissance)(シナリオプランニング): 意思決定を行う前に、起こりうる多様な未来のシナリオとそれぞれの確率を詳細に検討します。
- バックキャスティング : ポジティブな未来を想定し、そこから遡って目標達成に必要なステップを特定する手法です。
- プリモーテム : ネガティブな未来を想定し、なぜ失敗したかを想像することで、潜在的な障害を特定し、対策を講じる手法です。
- 10-10-10プロセス: 決定の短期的(10分後)、中期的(10ヶ月後)、長期的(10年後)な結果を考慮することで、時間的割引を克服し、熟慮的な思考を促します。
- 未来に焦点を当てるコミュニケーション: 他者とのコミュニケーションにおいて、過去の出来事を蒸し返すのではなく、将来の目標や行動に焦点を当てることで、防衛的態度を減らし、建設的な対話を促進します。
ピンと来ないものを説明しよう。
オデュッセウス契約
オデュッセウスのローマ名がユリシーズらしい。
オデュッセウス契約と言えば、
結構知っている人も多いだろう。
古代ギリシャの英雄オデュッセウスは、
航海の途中でセイレーンが住む危険な海域を通ることになりました。セイレーンの歌声は船乗りを魅了し、
船を座礁させてしまうことで知られていました。
オデュッセウスの決断と準備
オデュッセウスはセイレーンの歌声を聞きたいと強く願いましたが、
同時に安全に航海を続ける必要がありました。そこで彼は巧妙な計画を立てました。
- まず、部下たちにはセイレーンの歌声が聞こえないように耳栓をさせました。
- 次に、自分自身を船のマストにしっかりと縛り付けるよう部下たちに命じました。
- そして、「何があっても、私の縄を決して解くな」と強く指示しました。
セイレーンとの遭遇
セイレーンの海域に差し掛かると、
オデュッセウスはセイレーンの魅惑的な歌声を耳にしました。歌声に誘惑され、彼は身もだえしながら縄を解くように部下たちに懇願しましたが、
耳栓をした部下たちはその声を聞くことができず、
彼の指示を忠実に守り続けました。
かなり有名な話で、
色々な本に出てくる。
夜は眠いので難しいことはできない。
意思決定誓い瓶 (Decision swear jar) の「誓い瓶」って何?
誓い瓶(swear jar)さえ理解できれば、
このプロセスは理解できる。
「誓い瓶(swear jar)」の概念は、特定の国や宗教に限定された文化ではありません。
その起源は1890年代に「swear box(誓い箱)」という形で現れ、1910年代に広まりました。特に「swear jar(誓い瓶)」という言葉は、1980年代にアメリカで誕生し、人気を得たとされています。
宗教的な起源というよりは、行動修正や自己規律の手段として、特に家庭内で俗語や不適切な言葉遣いを減らすために使われるようになったものです。罰金を集めて慈善団体に寄付したり、特定の目的のために使われたりすることもあります。
したがって、特定の国や宗教に特有のものではなく、個人や家庭、コミュニティの中で自主的に取り入れられてきた習慣であると言えます。
Geminiに聞いたので間違っているかもしれないが、
とりあえず納得できるし、
意思決定誓い瓶もピンと来るはずだ。
明らかにやったほうが良いことを「めんどくさくてやりたくない」と思うのは典型的な誓い瓶だろうか。
例えば歯磨きとフロスである。
やらないほうがいいと思う人は存在するはずないが、面倒くさい。
終わりに
- 意思決定の質は結果の質とは異なります。 結果が良くても、必ずしも良い意思決定とは限りません。
- 良い意思決定は良いプロセスから生まれます。 自身の知識状態を正確に把握し、不確実性を受け入れ、多様な可能性を考慮することが大切です。
- 結果主義は意思決定の質を歪めます。 結果が良いと意思決定も良かったと誤解する傾向です。
- 人の認知バイアスが意思決定の質を下げます。 「確実性の幻想」や「自己奉仕バイアス」「ティルト」などが判断を鈍らせます。
- ティルトとは感情に流されて判断が損なわれる状態です。 感情の動揺が論理的な思考を妨げます。
- 「よくわからない」と言える勇気が良い意思決定につながります。 不確実性を受け入れることで、より客観的な判断が可能になります。
- あらゆる意思決定は将来への「賭け」と捉えられます。 常に予測に基づいていることを認識する視点を持つことが重要です。
- 結果が悪くても、意思決定プロセスが適切だったかを見極めましょう。 結果と意思決定を切り離して評価する姿勢が肝心です。
- 真実探求グループの規範「CUDOS」を活用しましょう。 情報共有、客観的な評価、中立性、批判的思考を通じて、質の高い意思決定を促します。
- 「心的時間旅行」で熟慮的な思考を促します。 過去や未来の視点を取り入れたり、事前準備をしたりすることで、感情に左右されない決定を目指します。
今回の記事では、私たちが日常生活で無意識のうちに行っている「意思決定」について、その「質」に焦点を当てて深掘りしました。単に結果が良かったか悪かったかだけで判断しがちな私たちですが、重要なのはその意思決定に至るプロセスそのものであるという点が、繰り返し強調されていましたね。
特に印象的だったのは、「結果主義(resulting)」という言葉です。私たちはどうしても目に見える結果に引きずられがちですが、プロセスが適切であれば、たとえ結果が思わしくなくても、それは「良い意思決定だった」と評価できる、という視点は、多くの場面で役立つ考え方だと感じました。
また、私たちの意思決定を妨げる様々な認知バイアスの解説も大変興味深かったです。特に「ティルト」のように、感情が判断を曇らせるメカニズムを知ることは、冷静な意思決定をする上で非常に重要だと改めて認識させられました。ポーカーの例は、LoLプレイヤーの方には特に共感できたのではないでしょうか。🤔
そして、意思決定の質を向上させるための具体的な戦略として紹介された「よくわからない」と素直に言える勇気や、「賭け」と捉える視点、さらには「CUDOS」の規範や「心的時間旅行」といったユニークなアプローチは、今日からでも実践できるヒントがたくさんありました。特に「ユリシーズ契約(事前約束)」は、感情に流されやすい私たちにとって、非常に有効な手段だと感じます。オデュッセウスの物語も、この概念を鮮やかに示してくれましたね。
この記事を通して、「良い意思決定」とは何か、そしてそれをどうすれば高められるのかについて、深く考えるきっかけになったのではないでしょうか。日々の選択の積み重ねが未来を形作ります。今回の学びを活かして、より質の高い意思決定を目指していきましょう!✨
人生最も大事なのは、
実行や行動である。
- やったか、やらなかったか
とりあえずLoLに限って言えば、
ダイヤモンド4もあれば
- 高い頻度でLoLを起動している
- ちゃんとゲーム内テキストを読んでいる
- ARの計算なども知っている
- アタックムーブもできる
少なくとも「やったか、やらないか」は
完璧にクリアしており、
やった側の人間だ。
今回書いた意思決定の質とは
- やり方
- あるいは、やった後の受け止め方
を洗練させていく項目になるだろう。
とりあえず、「やった後の話」になる。
ガレンJGは、
3:30が楽に切れるようなバフが来たら執筆したい。

